
2008/05/25作成
2008/06/12更新
杖バルの狩り
![]()
狩り方(応用編:杖バルPT)
| 今まで杖バルPTを組む機会など皆無でしたが、交流会のおかげで組める機会も増えてきました。 各々連携や役割分担など試行錯誤しながらのPTですが、改めてPT狩りの形を考える良い機会となりました。 LVや装備、ステ・スキルなどの違いはあるものの基本的には同じタイプ同士のPTなので、通常のPTのように明確に役割が分かれていません。 バインド一つとっても、攻撃としてのバインドもあれば、仮の足止めとしてのバインド、タゲ取りの為のバインド、そして誘導(モンスの追加)とそれぞれがその場の状況で役割を変えていくことになり、皆が攻撃役であり補助役でもあります。 とは言っても、同タイプのPTなので言わばソロの集合体です。 なので狩り方は基本編でも述べたような形の延長になります。 ソロの時に感じた「この場所にピンポイントで自分の分身(シャドウじゃないよw)が居たら・・・」という場面。これを補えるのがPTです。 一人では微弱な杖バルもそのメリットを最大限に生かして、さらに束になれば普通のPTでは出来ないような狩りが可能だと思います。 これから述べる事は私の『理想論』です。 書いてる本人でさえ完璧に出来たことはありません。<(_ _)> |
| 凡 例 |
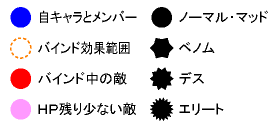 ※ 狩場はロン族の村を想定して作ってあります。 小さめの敵はチビロンを表しています。 |
| おさらいも兼ねて基本的な動きを確認します。 バインドの中心としていた敵が倒れ「次の中心をどこにするか」という良くある光景です。(図1) 敵1なら二匹が範囲に、しかしあと少しで倒せそうな敵が入ってますね。 敵2なら一匹しか入ってませんが硬いベノムです。(図2) |
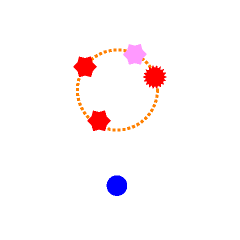 |
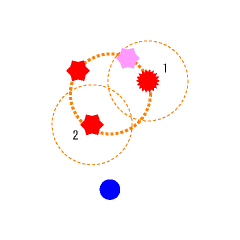 |
|
| 図1 | 図2 |
| どちらを中心に据えても”正解”です。 ですが応用編なので、さらに先の手を読んでみましょう。 あえて敵2を中心に置きます。その際、立ち位置がポイントです。(図3) 敵1はエリートなので周りの敵よりも先にバインドが切れて移動し始めます。二匹のベノムの間を通って来るように位置取りをして・・・ バインド範囲に入ったところで中心を切り替えます。(図4) モンスのランクによる効果時間の差を逆に利用した一手です。 |
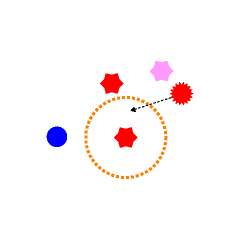 |
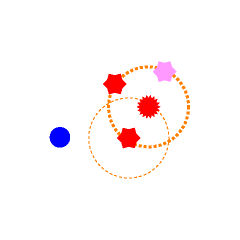 |
|
| 図3 | 図4 |
| 次は、二人で連携して敵を集める動きです。 バインド役とバインド中心を見て遠いサイドに集めるのがセオリー。(図5) バインド範囲に捕まえたら、すかさず一番殲滅に時間がかかりそうな新しい敵に中心を変えます。(図6) こうすることで後にドーナツ化するのを防ぐのが狙いです。 |
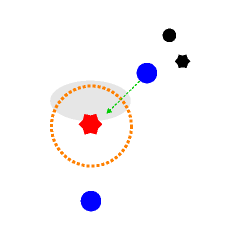 |
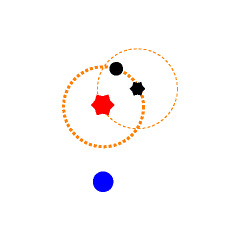 |
||
| 図5 | 図6 | ||
| さらにバインド役は集め役が次に入ってくるコースを見て立ち位置を変え、集め役はその空いたコースに連れてくるようにすることで、殲滅効率と安全確保を両立することができます。(図7) |
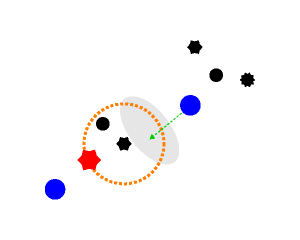 |
|
| 図7 |
| 余談ではありますが、立ち位置の話。 私の場合、バインド中心から近い位置に立つことが多いです。(図8のA) 理由はいくつかありますが、主には背後から新手の敵を呼び込まないように狩場の範囲を狭く保ちたいというのが一つ。 もう一つはバインド範囲外の敵を呼び込むのにワザと近めに立つというのがあります。(図8のコース1) ソロの場合は安全確保が第一なのでBの位置に立つこともありますが、PTの場合はAが囮、Bが援護ということもできるからです。 ※ いざという時のBの援護があってもAは大変危険です。(笑) HP・防御・回避・ダメ無効などに自信が無ければ安全策を取るべきです。 |
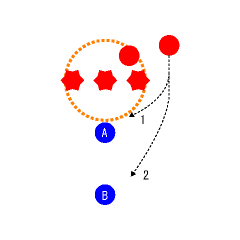 |
|
| 図8 |
| PT崩壊そして総崩れ・・・は大体以下のパターンが多いかと。 バインドの中心が早い段階で倒れドーナツ化する。(図9) とりあえず次の中心は手前のエリとしました。 が、後方の敵の一部はバインドが解けて順に動き出します。(図10) |
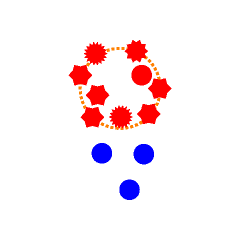 |
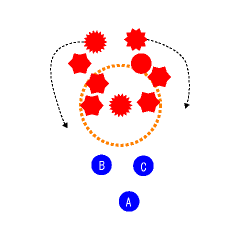 |
||
| 図9 | 図10 | ||
| 回り込もうとしてきた敵を「緊急予防措置」としてBは左から、Cは右からの敵に対応してそれぞれの敵から離れます。(図11) ですが、本来のバインド中心には入っていないので、バインドをし続けていないと当然また動き出します。(図12) さらには後方の残りも参入・・・じりじりと後退、そのまま総崩れ・・・ と、こんな感じでしょうか。 こうした場合、一旦後退して敵の数が少ない状態から徐々に集め直して立て直しした方が安全かもしれません。 |
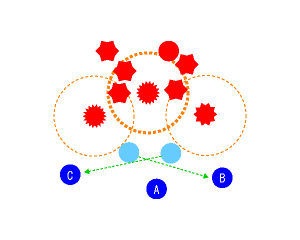 |
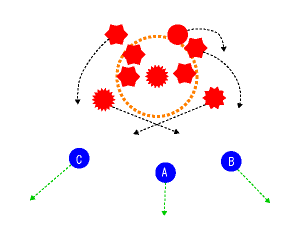 |
||
| 図11 | 図12 | ||
| 先に「一旦後退した方が良い」としましたが、この場面、その場で立て直すチャンスはありました。 その分岐点となったのは図10〜11のところだと思います。 まず回り込んだ敵をバインドするポイントをもう少し中にします。(図13) そしてそのまましばらく三点でバインド。(図14) 敵HPの減り具合を確認しながら最適なポイントを探します。 |
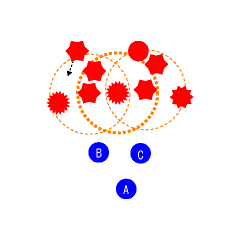 |
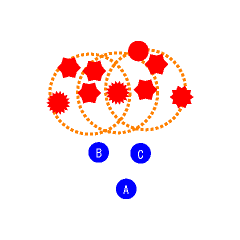 |
||
| 図13 | 図14 | ||
| 左側の敵の方が殲滅に時間が掛かりそうなのでバインド中心を左側に変えました。同時に立ち位置も移動。(図15) この時、右側の敵にバインドをしていた人(タゲを持っている人この場合AとCにあたる)はバインド中心を結ぶ延長線よりやや内側になるような位置取りをします。(図16) ※ 対象となる敵をバインド中心の延長線上つまり真反対に置いてしまうと、左右どちら回りで向かって来るのか予測が出来なくなってしまうから。 わざと近いコースを与えておくことで敵の行動をコントロールしやすくなります。 |
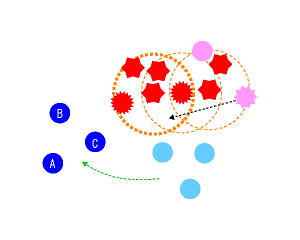 |
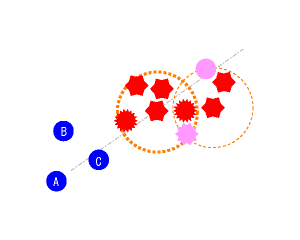 |
||
| 図15 | 図16 | ||
| タゲを持っている人はその敵に合わせて移動します。(AとC) この時タゲを持っていない人(この場面ではB)はバインドを切らさないように専念します。(図17) もしタゲがBに移ってしまった場合、安全になったAまたはCがバインド役となりBは敵を誘導しながら安全な位置まで移動します。 このように”攻守”の切り替えにすばやく対応出来るかがカギとなります。 重要なのは敵に追われるあまりに、パニックにならない事。 冷静に判断して、それでもダメな時は一次撤退(帰還)も必要です。 |
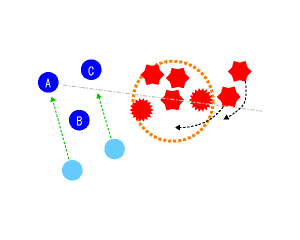 |
|
| 図17 |
| 敵をバインド範囲に誘導する場合、PTならば誰かが誘導役を務めれば良いわけですが、ソロ狩りの場合だとそう簡単にはいきません。 そこでシャドウを囮に使った誘導法をご紹介。 シャドウを出現させるとすぐに敵のタゲを取ってくれます。(図18) そうしたらバインド中心よりも遠いサイドで尚且つスペースのある側に近い敵にカーソルを合わせてシャドウを出し直します。 この時、シャドウが具現化するまでカーソルはそのままで。 ※ シャドウのタゲ取り効果はすさまじく、逆にシャドウからタゲを奪い返すのはほぼ不可能なくらいタゲを取ってくれます。 |
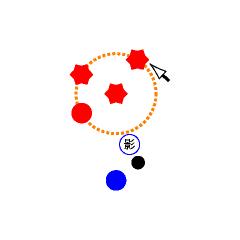 |
|
| 図18 |
| カーソルを当てた敵付近にシャドウが出現すると、シャドウはタゲを取った敵に向かって、敵はシャドウに向かって移動し始めます。(図19) 本人はシャドウが具現化した時点でバインドを再開します。 バインド範囲内にうまく捕らえる事が出来ればOK。(図20) うまく行かなかった場合は捕らえられるまでシャドウを出し直します。 この方法はソロの時だけでなくPTの時でも使えます。 但しPTの場合、何人もでシャドウを出してしまうとお互いにタゲを奪い合ってしまい、うまく誘導することが出来なくなりますので、なるべくシャドウを出す人は一人だけにした方が良いと思います。 また、ソロ・PTに限らずウェイル36以上ある人は、思わぬタイミングで即死効果が出てしまう事もあるので注意してください。 |
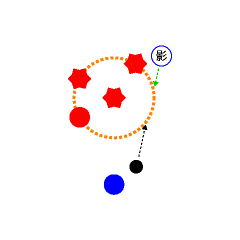 |
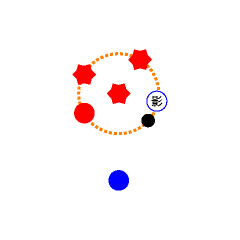 |
||
| 図19 | 図20 | ||
![]()